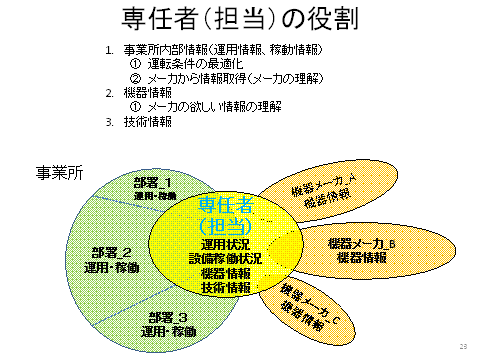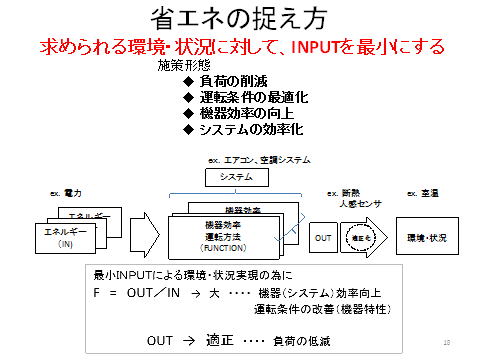
企業・施設の省エネ
企業・施設の省エネの進め方
機器の置き換えに目が行きがちですが、その前に現状の無駄を削減することから始めなければ結果としての
投資も効率が悪くなります。また、部分の最適化が必ずしも全体の最適化になるとは限らず、施設全体の
エネルギーフローを把握して適切な推進手順を考慮することが必要です。
省エネ推進 Step
Step-1 負荷の削減 ⇒ 全員参加によるムダの削減
<省エネ推進環境の整備>
従業員の「家庭の省エネ教育」
→気付き、感性を職場で展開
→トップの号令
→全員活動
Step-2 運転条件の最適化 ⇒ 省エネ担当(専任)者による運転条件の最適化
*省エネ担当(専任)者の育成
→設備の最適運用
Step-3 機器効率の向上 ⇒ 省エネ担当(専任)者・メーカの連携
*省エネ担当(専任)者の育成
→メーカとの連携
Step-4 システムの効率化 ⇒ 施設全体活動
◆ 省エネの捉え方
求められる環境・状況に対してINPUTを最小にするのが省エネです。
ここで、求められる環境を明確に定義する必要があります。
しかし、何を何時どの程度、そして季節や稼働状態を踏まえた時に、必要十分な状況を明確にすることは
簡単な事ではありません。実際は状況を想定して必要な状況を決めていく事が多いと思われますが、
どの様な想定を行ったが明確でない場合が多く、省エネ診断でもこの前提を確認することが最初に
すべきことです。
例えば. 求められる部屋の環境(温度、湿度、照度、清浄度 等)は部屋の使用目的で異なります
部屋の環境と言っても、広い部屋では状態の立体的分布も存在します
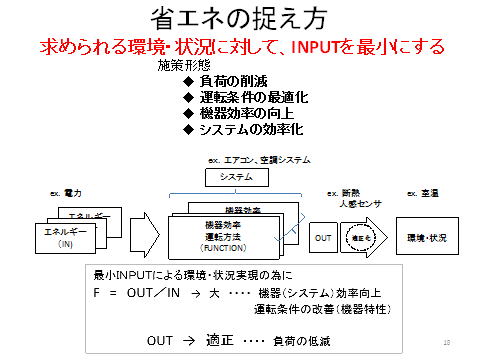
Step-1 負荷の削減
負荷の削減は、省エネ担当だけでできる事ではありません。従業員全員が省エネマインドを持ち、
日頃の気付きの中で対応し、提案していくべき内容です。
この意味から、従業員全員にまず家庭の省エネの教育・実践をお勧めしています。
家庭での省エネ活動は、光熱費の削減に繋がり、従業員の賛同も得やすい活動です。
この家庭での実践を通じて養われた省エネマインドを、職場で発揮することが重要です。
省エネは全体活動が重要で、トップの号令が大切と言いますが、振り向いてもだれも付いて
来てくれないでは掛け声だけで終わってしまします。
トップの号令に従業員が呼応してこそ、全体活動が可能になります。
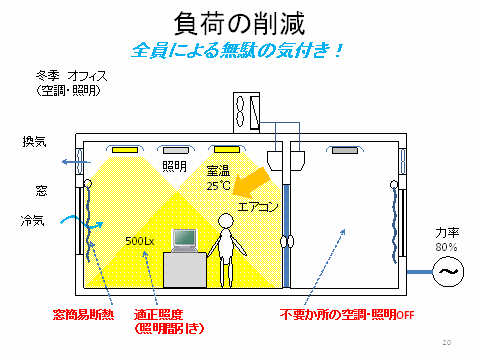
Step-2 運転条件の最適化
設備の運転条件の最適化は、設備の知識が必要です。一般論と、使用設備固有の技術情報を理解し、
運用するには設備担当が必要になります。
投資が必要な設備の更新、システムの最適化と省エネのレベルを上げていくうえで、省エネについての
理論的な内容と設備の知識がどうしても不可欠になります。メーカは扱う分野と商品についての知識は
あっても、決して現場全体を理解して最適な設備をて供することはできません。所属する現場に合った設備
の運用と将来的な導入を行うには、現場サイドで現場に精通し、メーカの力を引き出すことのできる
知識を持った担当が不可欠です。
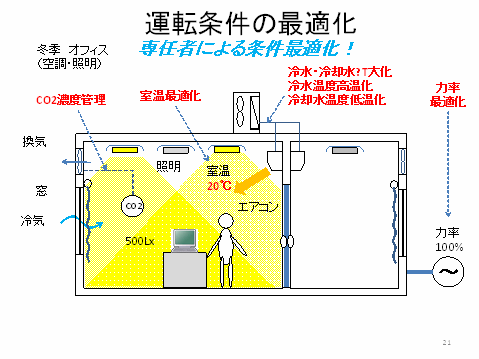
Step-3 機器効率の向上(設備の導入)
ここでは、効率の高い設備を導入することを意味しています。
3項で述べたように、有効な選択の為には情報の集約が必要になります
個々の設備については各論でご紹介します。
Step-4 システムの効率化
省エネの目的は、施設全体でとらえた時の年間の光熱費を削減することが目的になります。
この時、施設内の設備が相互に関連し合いながら機能している事を考慮して、最適な機器と制御の
選択が必要です。単独設備の効率が必ずしも全体の効率化に結びつかない場合もあります。
施設全体のエネルギーフロー、配管系統、建築構造 等々を把握する中で、全体最適化を図る
事が必要です。
半導体工場の例でご説明します
半導体工場のエネルギーフローを基礎設備を中心に描くと、概要は以下の様に表わすことができます。
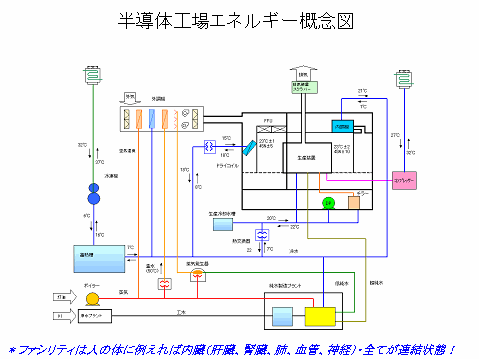
基礎設備の主要機能ごとにくくると以下の様に要素機能を示すことができます

この図でわかる様に、個々の機能を果たす為に、複数の設備・要素機能が相互に関連しています
工場全体の省エネを分解すると、この要素機能をその目的に応じて最適化することにブレークダウン
することができ、その要素機能を最適化するために、要素機能を構成する機器の関係や要素機能同志、
の関係を最適化することが必要になります。
この関係を、半導体工場の主要な機能である装置発熱の処理について示すと以下の様になります。
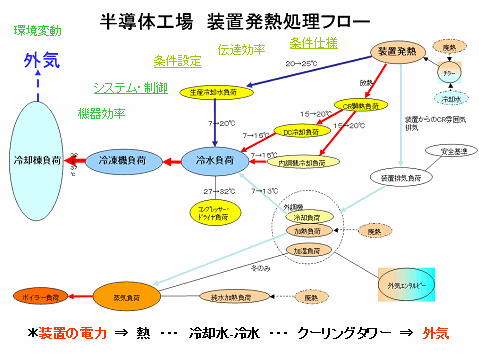
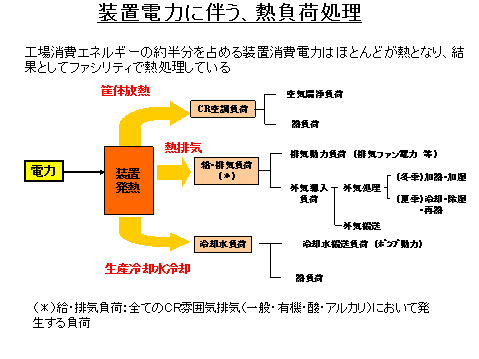
施設(工場)の省エネの最適化を進めるには、機器相互の関係を把握し対策を考えることの必要性の
一端をご説明しました。
施設のエネルギー解析をする上では、熱・流体・電気の理論、機器の方式・構造についての知識、
制御方法についての知識が必要になります。この意味から、省エネの進展に伴い、担当・専任者の
教育が大変重要です。
6.専任者の必要性
3項以降で、担当、専任者の必要性をご説明しました。
添付の図にもある様に、運用方法、機器の配置他施設の内情については施設の所属員でしか
把握できないのは言うまでもありません。メーカはメーカの商品についての知識しかないのは
致し方ない事です。この事から、施設の内部を知る者が、設備を理解して最適な設備の導入に
結びつけるしか方法がありません。この意味から、省エネの推進には技術と設備に精通した担当、
専任者が不可欠です。